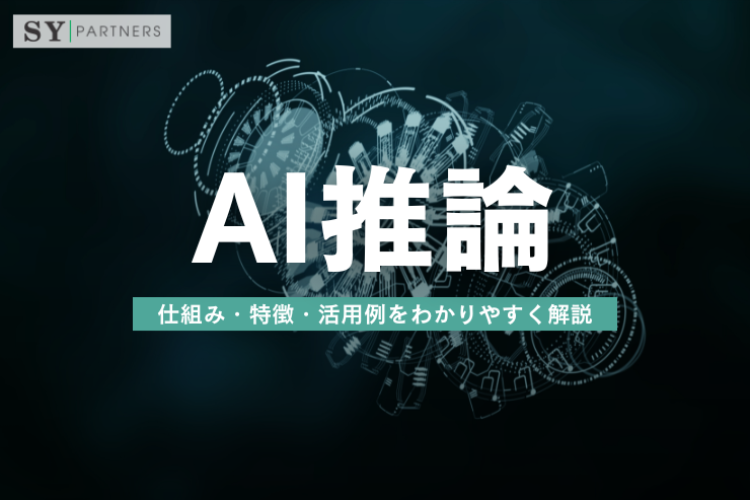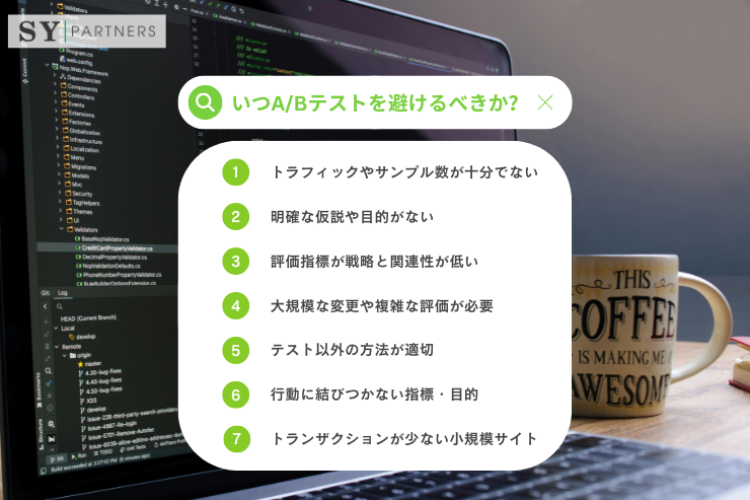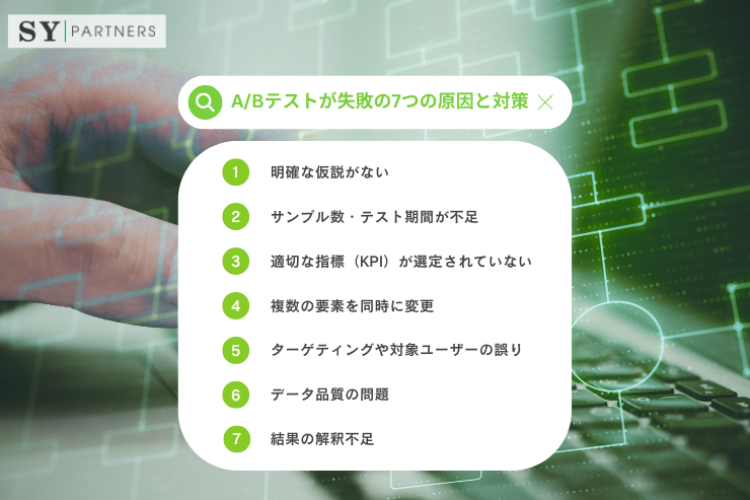AIは本当に理解しているのか?生成AIの錯覚と信頼できる判断軸
生成AIが自然で一貫した文章を返すようになり、「AIは理解しているのではないか」という感覚が広がっています。会話が成立し、論理的に説明され、こちらの意図を汲んだように見えるほど、人は相手に“理解”を推定しやすくなります。これは人間同士の対話で働く信頼判断の癖が、そのままAIにも適用されるためです。
一方で、実務で重要なのは哲学的な「理解の有無」よりも、どの条件で信頼でき、どの条件で破綻しやすいかを把握し、運用で制御できる状態を作ることです。生成AIは流暢さや論理形式で説得力を作れる反面、根拠が曖昧でも埋めてしまう性質があり、ハルシネーション(もっともらしい誤り)を起こします。ここを情緒で判断すると、期待値管理が崩れ、成果物の品質と説明責任が不安定になります。
信頼はモデル性能だけでなく、検証可能性・リスク・入力条件の制御・再現性・改善サイクルによって段階的に設計できます。AIを「理解しているかどうか」で語るのではなく、「理解して見える」状態を前提に、ガードレールと運用ルールで過信を抑えることが、実務で成果を安定させる現実的なアプローチになります。


 EN
EN JP
JP KR
KR