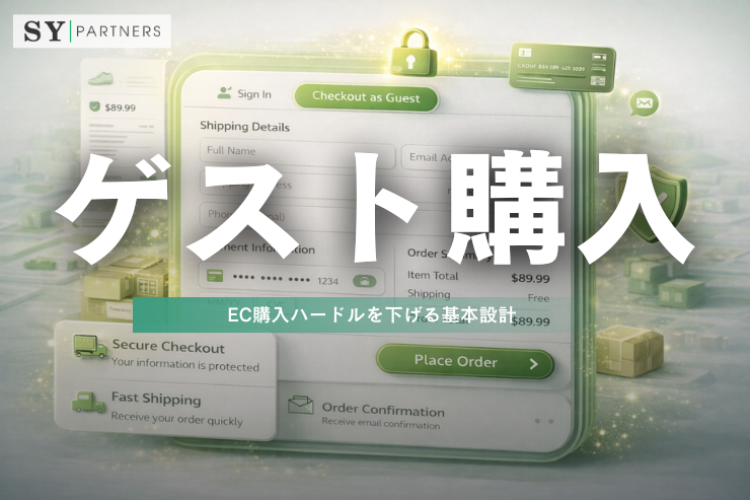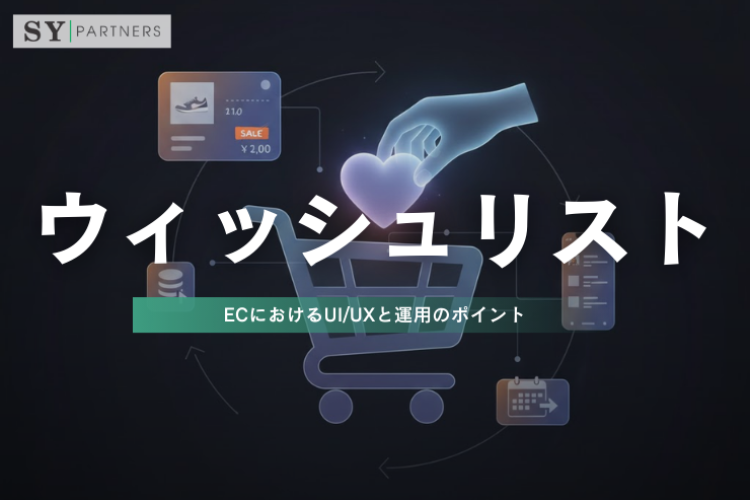Golang(Go言語)とは?特徴・他言語比較・注意点と活用分野を解説
Golang(Go言語)は、「大規模開発でも壊れにくく、運用しやすいバックエンドを速く作る」ことを強く意識して設計された言語です。構文や言語仕様を必要最小限に抑え、書き方の自由度をあえて広げすぎないことで、チーム開発における「読みやすさ」と「統一感」を作りやすくしています。結果として、個人の癖や流派による差が出にくく、コードレビューや保守のコストが安定しやすいのが特徴です。
さらにGoは、単一バイナリで配布できる点や、依存関係を抱えにくいビルド/実行形態を取りやすい点から、デプロイや運用が軽くなりやすいです。コンテナ環境・クラウド環境・マイクロサービスのように、サービス数が増えたり環境が複雑になったりするほど、こうした性質が効いてきます。また、goroutine と channel を中心とした並行処理モデルにより、高トラフィックなAPIやネットワーク処理を「設計として扱いやすい形」にしやすいのも、Goがバックエンドで支持される理由のひとつです。
本記事では、Go言語の基本的な考え方を整理しつつ、主な特徴、他言語との比較、導入時に押さえるべき注意点、そして実務で使われやすい活用分野までをまとめます。「Goが向く要件・向かない要件」を判断できる状態をゴールに、運用を前提とした視点で解説していきます。


 EN
EN JP
JP KR
KR