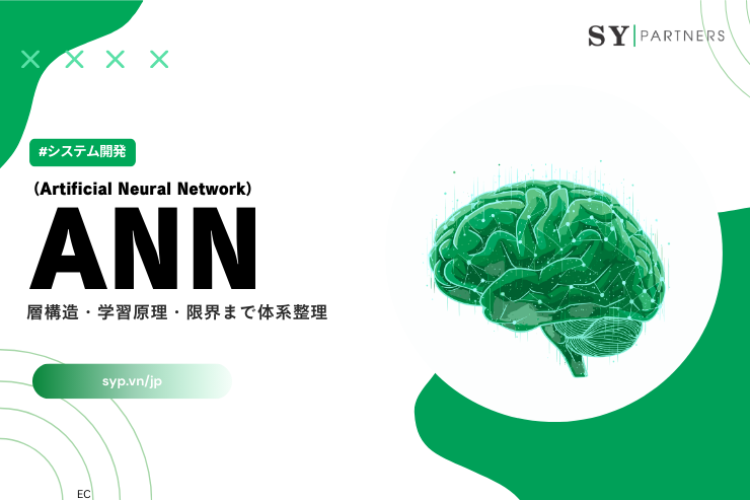テスト設計の原則:品質を偶然に委ねないための思考と構造
テストは「やった・やっていない」ではなく、「どう設計したか」で品質が決まります。テスト件数やカバレッジが増えると、努力量は可視化されますが、守れている品質の輪郭まで自動的に明確になるわけではありません。むしろ、設計のないまま増えたテストは、重複と抜けを同時に抱え込み、実施コストと保守コストだけを増幅させます。その結果、回帰テストは遅れ、検知は後ろへずれ、修正コストは上がり、品質は「たまたま大丈夫だった」に寄っていきます。品質を偶然に委ねないとは、テストを作業ではなく構造として捉え、意図したリスクを意図した粒度で潰せる状態を作ることです。
本記事では、テスト設計の原則を「テスト工程全体の流れ」の中に置き直し、テスト設計とテストケースを混同しないための整理を行います。そのうえで、目的から逆算して観点を固定し、網羅性と効率を両立させ、再現性と学習性を持ったテスト資産へ育てるための手法と判断基準を解説します。さらに、リスクベースドテストの考え方、良いテストケースの条件、そして設計が弱い組織でテストが負債化する典型パターンまで踏み込みます。テストを「頑張り」から解放し、誰が担当しても同じ品質水準へ収束できる仕組みに変えることが狙いです。


 EN
EN JP
JP KR
KR