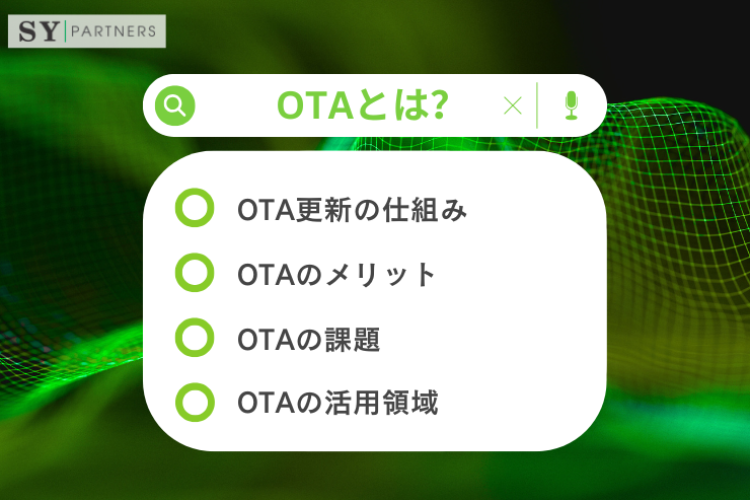シングルサインオン(SSO)基礎と導入戦略:安全性と利便性を両立する実践ガイド
情報システムが多様化する中で、複数のサービスに対して個別に認証を行うことは、ユーザーにとって大きな負担となります。特に企業や教育機関では、従業員・学生・管理者など多数の利用者が日常的に複数システムへアクセスするため、ログインの煩雑さが生産性低下の一因となります。
こうした課題を解消するために広く採用されているのが、シングルサインオン(Single Sign-On, SSO)です。SSOを導入することで、ユーザーは一度の認証で複数のアプリケーションやサービスへ安全にアクセスできるようになります。利便性の向上に加え、パスワード管理の負担軽減や不正アクセス防止にも貢献するため、組織全体のセキュリティ向上にもつながります。
本記事では、SSOの定義や基本的な仕組み、認証プロトコルの種類、導入時の注意点に加え、他の認証方式との比較や利点・課題についても整理します。さらに、組織の規模や運用体制に応じた実践的な導入戦略を専門的な観点から解説し、セキュリティとユーザー利便性を両立させるための具体的な指針を提示します。


 EN
EN JP
JP KR
KR