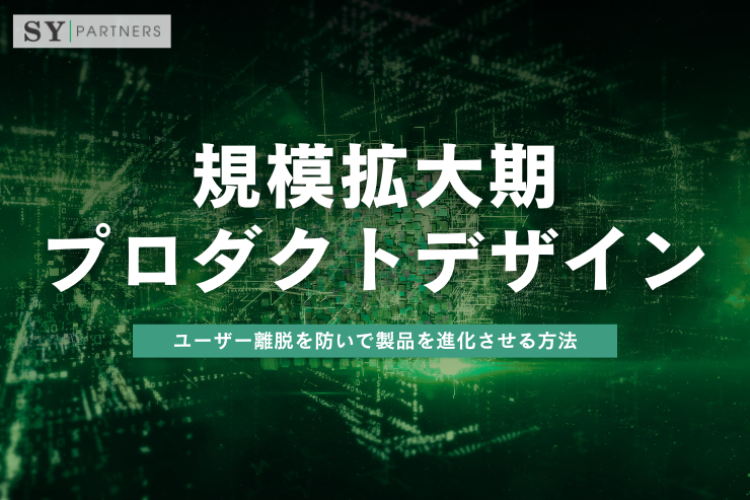Core Web Vitalsとは?SEO成果につながる指標(LCP・INP・CLS)と改善の実務
Web体験の品質は、ページがどれだけ早く表示されるかだけで決まるものではありません。表示された内容が安定しており、操作に対して違和感なく反応するかどうかまで含めて、ユーザーは一連の体験として評価します。Core Web Vitalsは、こうした体感的な品質を、LCP・INP・CLSという3つの観点に分解し、定量的に捉えるための指標群です。
Core Web Vitalsが特徴的なのは、通信速度や実装効率といった技術内部の指標ではなく、実際のユーザー行動と知覚を前提に評価される点です。75パーセンタイルを基準としたフィールドデータにより、極端な環境ではなく、多くのユーザーがどのような体験をしているかを把握できます。これにより、UX改善とSEO評価を同じ文脈で扱うことが可能になります。
本記事では、Core Web Vitalsの基本的な考え方を起点に、各指標の意味や評価基準、計測方法を整理します。そのうえで、LCP・INP・CLSそれぞれについて、実務で意識すべき改善の考え方と具体的なアプローチを解説します。あわせて、SEOとの関係性や、改善を継続的に回していくための運用設計にも触れ、指標を「測って終わり」にしないための視点を提示します。


 EN
EN JP
JP KR
KR