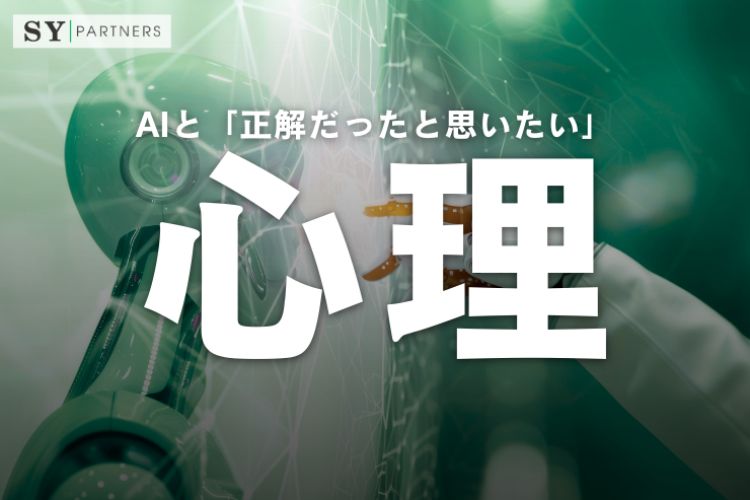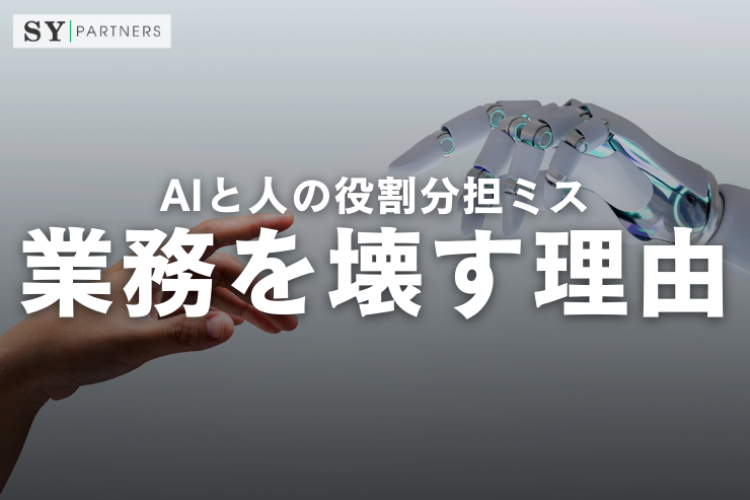AIチャット接客はCVRを改善するのか?効く条件と実務設計
ECやSaaSで「流入はあるのに売上が伸びない」と感じるとき、ボトルネックは購入直前の迷いであることが多いです。ページに情報を増やしても、読む負担が上がるほど「確認したいのに読み切れない」状態が増え、比較タブだけが積み上がって決めきれなくなります。迷いが強い人ほど「後で考える」に逃げやすく、そのまま戻らないケースが増えます。結果として、広告や露出を増やしてもCVRの天井だけが残りやすく、施策の費用対効果が見えにくくなります。
問い合わせを送れば解決するように見えても、返信までの待ち時間で熱量が落ちる問題が残ります。返信が来た頃には別の候補へ移っていたり、比較の前提が変わってしまったりして、結局は購入へ戻らないこともあります。さらに、問い合わせの内容が「返品は可能ですか」「いつ届きますか」「互換性は大丈夫ですか」のように購入直前の不安へ集中している場合、返信の遅さそのものが離脱要因になっています。迷いを解けるタイミングを失うほど、CVRは改善しにくくなります。


 EN
EN JP
JP KR
KR