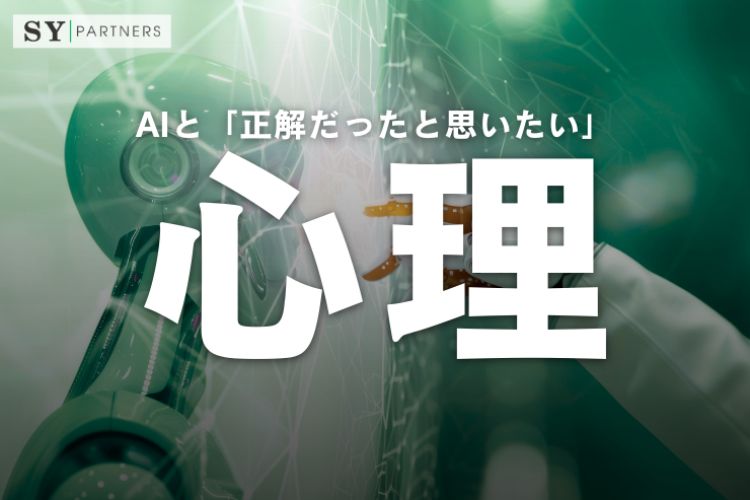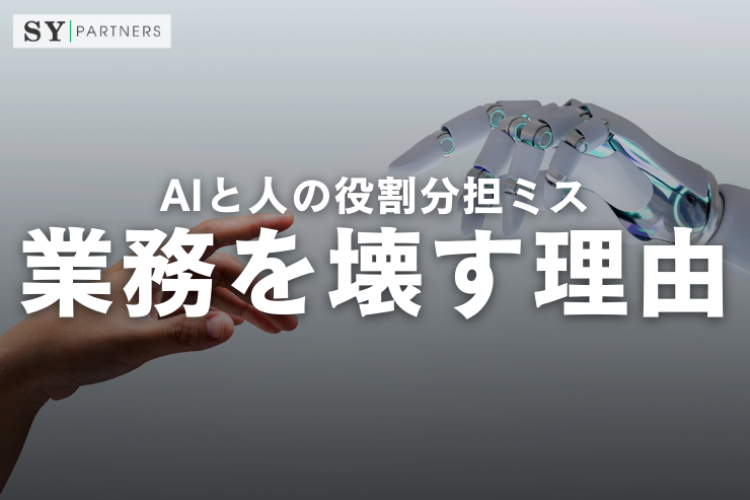破滅的忘却(Catastrophic Forgetting)とは:継続学習における知識喪失の核心問題
人工知能(AI)が人間のように学習を重ねるためには、「新しい知識を獲得しながら過去の知識を保持する」能力が不可欠です。しかし、従来の機械学習モデルでは、新しいタスクを学習する際に以前の知識を急激に失う現象が存在します。これが「破滅的忘却(Catastrophic Forgetting)」と呼ばれる問題です。
破滅的忘却は、特に継続学習(Continual Learning)や終生学習(Lifelong Learning)の文脈で深刻な課題となります。新しい情報が既存のモデルパラメータを上書きすることで、AIは過去の知識を失い、安定した長期運用や汎用的な知識活用が困難になります。
この課題に対処するため、リプレイ法や正則化法、動的構造法など多様な防止手法が研究されています。本記事では、破滅的忘却の定義・メカニズム・影響・検出方法・防止手法を包括的に整理し、理論的意義と今後のAI研究への展望を明確に解説します。
1. 破滅的忘却(Catastrophic Forgetting)とは
1.1 定義
破滅的忘却とは、ニューラルネットワークが新しいタスクを学習した際に、以前に習得したタスクの知識を急速に失う現象を指します。これは、学習済みの重みが新しい学習データに最適化される過程で上書きされることによって生じます。
1.2 現象の特徴
この現象は「段階的」ではなく「急激」に発生する点が特徴的です。つまり、新しいデータを数回学習するだけで、以前のタスクに対する性能が劇的に低下します。従来の学習アルゴリズムでは、タスク間の関係性を考慮せずに最適化が行われるため、このような忘却が避けられません。
2. 破滅的忘却が発生する要因
破滅的忘却(catastrophic forgetting)は、継続学習やメタ学習において避けられない現象の一つです。モデルが新しいタスクを学習する際に、既存タスクで得た知識を失ってしまう問題であり、その原因を理解することは効果的な継続学習設計に不可欠です。以下に主な要因を整理します。
2.1 パラメータ共有の影響
ニューラルネットワークでは、複数タスク間でパラメータを共有する構造が一般的です。新しいタスクを学習する際に共有パラメータが更新されると、過去タスクで重要だった情報が上書きされやすく、特に全結合層や畳み込み層の共有が多い深層ネットワークでは影響が顕著になります。
この問題を緩和する手法として、重要度に応じたパラメータ保護(例:Elastic Weight Consolidation, EWC)や、タスク専用のパラメータ分離手法が有効です。これらのアプローチにより、各タスクの重要パラメータを保持しつつ、新規タスクの学習を行えるため、新旧タスク間の干渉を最小化しながら継続学習を可能にします。
さらに、パラメータ分離と重要度保護を組み合わせることで、共有層の有効活用と知識保持のバランスを取ることができ、モデル全体の学習効率も向上します。
2.2 タスク独立性の欠如
タスク間の関係を明示的にモデル化できない場合、新規タスクの学習は既存タスクの表現空間を破壊するリスクがあります。タスクの境界や特徴が不明確だと、ネットワークは適切な適応先を判断できず、既存知識が上書きされやすくなります。
この課題に対する有効なアプローチとして、タスク識別器を備えたマルチヘッドアーキテクチャや、注意機構を用いたタスク依存の重み調整が挙げられます。これらの手法により、各タスクの独立性を維持しながら、新しい知識を既存表現に干渉させずに統合可能です。
さらに、タスク依存重みの調整は、過去タスクの重要度に応じて学習率やパラメータ更新を制御できるため、破滅的忘却の抑制と新規知識の効率的獲得を同時に実現できます。
2.3 データ非同時性
継続学習環境では、しばしば過去のデータセットに再アクセスできない制約が存在し、全てのタスクを同時に学習することが困難です。この制約により、モデルは新しいタスクやデータに過剰適応しやすくなり、その結果、旧タスクで獲得した重要な知識が失われやすくなります。特にタスク間で共通する特徴やパターンが少ない場合、破滅的忘却の影響は顕著になります。
この問題への対応策としては、リプレイ手法や生成モデルを用いたデータ補完が有効です。リプレイ手法では、過去タスクの一部データや特徴表現を保持し、新しいタスク学習時に再利用することで、旧タスクの情報をモデルに反映させ続けることができます。一方、生成モデルを用いるアプローチでは、過去タスクのデータを擬似的に再構築し、メモリ効率を保ちながら忘却を防ぐことが可能です。
このように、非同時性による学習制約の影響を緩和し、部分的にでも過去データを利用できる環境を整えることが、継続学習における忘却抑制の重要なポイントとなります。適切なリプレイや生成手法の組み合わせにより、モデルは新規タスクに適応しつつも、旧タスクの知識を効率的に保持できるようになります。
2.4 モデル容量の不足
モデルの表現力がタスク数やデータの複雑さに対して不足している場合、各タスクの特徴やパターンを十分に捉えられず、結果として旧タスクの知識が上書きされやすくなり、破滅的忘却が発生しやすくなります。特に、パラメータ数や層数が限られた小規模モデルでは、学習可能な情報量に制約があるため、複数タスクを効率的に学習することが困難になります。
この課題への対応策としては、まずモデル容量の拡張が考えられます。パラメータ数を増やす、層数を深くするなど、モデルの表現力を向上させることで、各タスクに必要な知識を保持しやすくなります。さらに、動的ネットワーク拡張手法(例えばProgressive Neural Networks)を導入することで、新しいタスクごとに追加のモジュールや層を組み込み、既存モジュールとの干渉を最小化しながら学習を進められます。
これにより、限られたモデル容量でも新旧タスクの知識を両立させやすくなり、長期的な継続学習環境においても破滅的忘却を抑制しつつ高い性能を維持できます。さらに、動的拡張を取り入れることで、将来的なタスク増加にも柔軟に対応可能となります。
2.5 タスク間干渉の高頻度
タスクが連続的かつ高頻度で与えられる環境では、破滅的忘却のリスクが一層顕著になります。学習間隔が短い場合、モデルは直近のタスクに過度に適応しやすく、既存タスクで獲得した重要な知識が急速に失われる傾向があります。この状態が続くと、新規タスクの学習効率も低下し、モデル全体の性能が不安定になる可能性があります。
この問題に対処するためには、学習スケジュールの最適化が有効です。タスクの優先度や重要度に応じて学習順序や学習時間を調整することで、モデルが過去の知識を保持しつつ新しい情報を効率的に取り入れられるように設計できます。加えて、メタラーニング手法による適応率の調整も有効です。各タスクに対してパラメータの更新量や学習率を動的に制御することで、新しい知識の吸収と既存知識の保持のバランスを最適化できます。
これらのアプローチにより、モデルは短期間で多数のタスクを学習する環境下でも、過去の知識を損なわず、長期的に安定した性能を維持することが可能となります。さらに、タスク間干渉を抑制することで、将来的な新規タスクへの適応もスムーズに行えるようになります。
破滅的忘却は、パラメータ共有、タスク独立性の欠如、データ非同時性、モデル容量不足、タスク間干渉など、複数の要因が重なって発生します。各要因を理解し、適切なアーキテクチャや学習手法を導入することが、継続学習モデルの安定性と長期的性能を確保する鍵となります。
3. 破滅的忘却の影響
破滅的忘却は、継続学習において避けがたい課題の一つであり、モデルが新しいタスクに適応する過程で、既存の知識を失う現象です。これによりAIシステムの実用性や信頼性が損なわれるため、その影響を正確に理解することが不可欠です。
3.1 性能低下
破滅的忘却(Catastrophic Forgetting)は、新しいタスクの学習中に旧タスクで重要だったパラメータが上書きされることによって引き起こされます。その結果、新しいタスクの性能は向上する一方で、旧タスクの精度が著しく低下することがあります。
特にマルチタスク環境では、タスク数が増えるほどこの影響が累積し、モデル全体の性能が不安定になります。旧タスクの知識が保持されないまま進行すると、再学習が必要となり、学習効率や計算コストが大幅に悪化します。
この問題を防ぐためには、定期的なリプレイ(経験再利用)や、パラメータの重要度に基づく知識保護手法(例:EWCやSI)を組み込むことが重要です。これにより、新規タスク学習中も旧タスクの情報を維持でき、長期的な継続学習環境でもモデル性能を安定させることが可能です。
3.2 知識継承の阻害
破滅的忘却によって過去の学習成果が失われると、モデルは既存知識を活かせず、新タスクに対してもほぼ一から学習し直す必要が生じます。この結果、再学習にかかる計算リソースや学習時間が増大し、運用効率が大きく低下します。
特に産業用AIや医療AIのような長期運用が前提のシステムでは、知識の継承が阻害されることで、精度維持と運用コストの両面に深刻な影響を与えます。モデルの性能が時間とともに不安定になるリスクも高まります。
このため、過去データの適切な保存や、重要パラメータの保護を組み込んだ学習設計が不可欠です。例えば、Elastic Weight Consolidation(EWC)やSynaptic Intelligence(SI)などの正則化手法、経験再利用(リプレイ)戦略を活用することで、過去タスクの知識を保持しながら新規タスク学習を効率的に進められます。
3.3 適応性の欠如
破滅的忘却が頻発するモデルでは、過去の知識が失われる一方で新タスクに過度に適応してしまうため、長期的な環境変化への柔軟な対応力が低下します。結果として、未知の状況や新規データに対してモデルが適切な判断を下すことが難しくなります。
この問題は、自律ロボット、自然言語処理モデル、医療診断AIなど、継続的な知識更新と適応が求められる分野で特に深刻です。こうした環境では、単に新しい情報を学習するだけでなく、過去の知識を維持しつつ新知識を統合するバランスの取れた学習戦略が不可欠です。例えば、正則化手法やリプレイ戦略、モジュラーアーキテクチャの導入により、過去タスクの干渉を抑えつつ適応性を確保できます。
このように、破滅的忘却への対策は、モデルの長期運用性・汎用性・信頼性を維持するための基盤となります。
3.4 モデル安定性の低下
破滅的忘却は、モデルの予測挙動を不安定にし、運用環境での信頼性を大きく低下させる重大な問題です。特に、意思決定支援システムや自律制御システムでは、この不安定性が安全性に直結するリスクを引き起こします。学習を重ねるたびに重要なパラメータが更新され、過去タスクの知識が失われることで、モデルの出力が予測不能になりやすいのが原因です。
この問題に対処するためには、タスクごとの重要度評価や正則化手法の導入が有効です。重要なパラメータの更新を制御することで、過去の知識を保持しつつ新しいタスクを学習でき、モデルの予測挙動を安定化させることが可能になります。また、リプレイ戦略やモジュラーアーキテクチャと組み合わせることで、安定性と適応性を両立させ、長期的に信頼できる運用を実現できます。
3.5 知識分散の非効率化
破滅的忘却が頻発すると、モデル内部の知識分布が偏り、特定タスクに依存した構造が形成されやすくなります。その結果、新しいタスクの学習効率が低下し、モデル全体の汎化性能にも悪影響を与えます。
この影響を抑えるには、メタ学習やリプレイバッファの活用が効果的です。これらの手法により、過去タスクの知識を均等かつ持続的に保持でき、タスク間の干渉を最小化できます。結果として、モデルは新規タスクを学習する際も既存知識を損なわず、効率的に学習を進められ、長期的な性能の安定性が確保されます。
3.6 長期的運用コストの増加
破滅的忘却が改善されない場合、モデルの運用期間が長くなるほど再学習や補正の頻度が増加します。これに伴い、計算資源の消費や追加データの収集、評価作業の負荷が累積し、システム全体の運用コストが大幅に上昇します。
特に、企業や研究機関で長期的にAIモデルを活用する場合、運用効率を考慮した設計と継続的評価体制の構築が不可欠です。破滅的忘却への対応が不十分だと、モデルの信頼性低下や運用コストの増大につながるため、初期設計段階から忘却抑制手法やモニタリング体制を組み込むことが、長期的なAIシステムの安定性と効率性を確保する鍵となります。
破滅的忘却は、性能低下、知識継承の阻害、適応性欠如、モデル安定性低下、知識分散の非効率化、長期的運用コスト増加など、多面的な影響を及ぼします。これらを理解し、適切な設計や防止策を講じることが、継続学習AIの実用性と信頼性を確保する鍵となります。
4. 破滅的忘却の検出と評価
破滅的忘却の影響を抑えるためには、まずその発生を正確に把握することが不可欠です。定性的な観察だけでなく、タスクごとの性能を定量化し、モデルがどの程度古い知識を保持しているかを評価する必要があります。
適切な評価指標の選定により、改善策の効果を測定することも可能になります。
4.1 訓練後性能差(Performance Drop)
訓練後性能差は、モデルが新しいタスクを学習した後に、旧タスクの精度がどの程度低下したかを測定する指標です。これにより、破滅的忘却がどのタスクで特に顕著に発生しているかを定量的に把握できます。
特に、マルチタスク学習や順次学習の環境では、旧タスクのパフォーマンス低下が累積することがあり、訓練後性能差の評価は運用上重要です。この指標を用いることで、モデル設計やハイパーパラメータ調整が忘却抑制に与える影響も定量的に比較可能です。
評価には、各タスクのテストセットでの精度やF1スコアが用いられるのが一般的です。また、タスク間の性能低下をグラフ化して可視化することで、どのタスクが他のタスクに影響を受けやすいかを直感的に把握でき、継続学習モデルの改善や学習戦略の最適化に活用できます。
4.2 累積誤差(Cumulative Error)
累積誤差は、全タスクにわたる予測誤差の総和を観察する指標であり、モデル全体の健全性を評価するうえで重要です。破滅的忘却が進行すると、単一タスクだけでなく全体の性能も低下するため、この指標を用いることで長期的な学習プロセスにおける誤差の蓄積傾向を把握できます。
また、累積誤差の分析により、改善が必要なタスクやモデルの特定の部分を明らかにすることが可能です。特定タスクだけでなく、モデル全体の知識保持状況や干渉の影響を定量化できる点が特徴です。
さらに、累積誤差を時間軸に沿って追跡することで、どの学習ステップで知識喪失や性能低下が顕著に発生しているかを特定できます。これにより、学習戦略やタスク順序の改善、ハイパーパラメータ調整などに活かすことができ、継続学習モデルの安定性向上に貢献します。
4.3 忘却率(Forgetting Rate)
忘却率は、初回学習後と再評価時のスコア差をもとに、モデルがどれだけ知識を失ったかを定量化する指標です。この指標により、単純な精度低下だけでなく、タスク間での知識保持能力の相対的評価を行うことができます。
特に、複数タスクや長期継続学習環境では、忘却率はモデルの耐久性や安定性を把握するうえで重要です。また、異なる学習戦略や正則化手法、リプレイ手法の効果比較にも活用でき、手法の改善や選択の判断材料となります。
さらに、忘却率を詳細に解析することで、知識保持の弱点がどの層やパラメータに起因するかを特定可能です。これにより、モデル設計やパラメータ調整の具体的な改善指針を得られ、破滅的忘却抑制の精度向上につなげることができます。
4.4 追加評価指標:再学習効率(Rehearsal Efficiency)
再学習効率は、破滅的忘却を抑制する手法の効果を定量的に評価する指標の一つです。具体的には、モデルが過去タスクを再学習する際に、どれだけ迅速かつ正確に性能を回復できるかを測定します。
この指標を用いることで、限られたメモリ環境下でのリプレイ戦略やタスク分離の有効性を明確に評価できます。再学習効率が高いモデルは、破滅的忘却への耐性が強く、タスク間干渉が少ないことを示します。
さらに、再学習に必要なデータ量や計算リソースとの関係を分析することで、コストパフォーマンスの観点からもモデルの評価が可能です。これにより、精度維持と計算効率のバランスを考慮した継続学習戦略の最適化に役立ちます。
4.5 追加評価指標:知識保持スコア(Knowledge Retention Score)
知識保持スコアは、過去タスクの性能をモデル全体のパフォーマンスと比較し、どの程度知識が維持されているかを数値化する指標です。このスコアにより、単純な忘却率だけでは把握しにくい、タスク間の相対的な知識保持状況を可視化できます。
特に、継続学習環境でタスク間干渉が大きい場合には、知識保持スコアを活用することで、どのタスクの知識が優先的に失われやすいかを特定可能です。これにより、忘却が発生する箇所に応じた対策やモデル調整を計画できます。
さらに、知識保持スコアを長期的に追跡することで、モデル設計や学習戦略の改善に活用できます。例えば、リプレイや正則化の効果を定量的に評価したり、タスク追加時のパラメータ調整方針を決定する際の指標として利用でき、継続学習モデルの性能維持に貢献します。
破滅的忘却の評価には、訓練後性能差、累積誤差、忘却率に加え、再学習効率や知識保持スコアなど複数の指標を組み合わせることが有効です。これにより、モデルの知識保持能力を定量的に把握でき、継続学習AIの安定性向上や設計改善に直結する情報を得ることが可能となります。
5. 破滅的忘却を防ぐ主な手法
破滅的忘却を効果的に抑制するためには、学習アルゴリズムやモデル設計に工夫を施す必要があります。単に新しいタスクを学習するだけでは、既存知識が失われるリスクが高いため、複数の手法を組み合わせるアプローチが推奨されます。ここでは、正則化、リプレイ、モジュラーアーキテクチャを中心に解説します。
5.1 正則化ベースの防止策
正則化ベースの手法は、ニューラルネットワークのパラメータ更新を制御し、過去タスクで重要なパラメータの変化を最小限に抑える方法です。これにより、新しいタスクを学習しても、既存タスクの知識が失われにくくなります。
代表的な手法として、EWC(Elastic Weight Consolidation)があります。EWCでは、各パラメータの重要度を定量化し、重要な重みの変化に制約をかけることで、忘却を抑制します。これにより、新規タスクの学習と既存知識の保持を両立できます。
また、SI(Synaptic Intelligence)は、学習過程で各パラメータがタスク達成にどれだけ貢献したかを評価し、重要度に応じて更新を制限します。SIも同様に、学習効率を損なわずに知識保持を実現できる点が特徴です。
さらに、正則化手法は他の破滅的忘却抑制手法と組み合わせやすく、EWCやSIを拡張したハイブリッドモデルも研究されています。これにより、複数タスク環境においても、パラメータの安定性と学習の柔軟性を両立できる点が大きな利点です。
5.2 メモリリプレイ手法
メモリリプレイは、過去タスクのデータや特徴表現を一部保持し、新しいタスク学習時に再利用する手法です。これにより、新規学習中に旧タスクの知識が失われることを防ぎ、破滅的忘却の抑制に寄与します。
具体例として、Experience Replayでは、過去の実データサンプルをランダムに再提示することで、旧タスクの精度低下を防ぎます。これにより、新タスクを学習しながらも、過去タスクの知識を効率的に保持することが可能です。
一方、Generative Replayでは、生成モデルを用いて過去タスクのデータを擬似的に再構築します。これにより、メモリ容量を大幅に節約しつつ、古い知識を学習に反映させることができます。特に、大規模タスクや長期学習環境で有効です。
さらに、近年の研究では、リプレイするサンプルの選択戦略や重み付けを工夫することで、限られたメモリ容量でも忘却を最小化する手法が提案されています。これにより、複数タスクが存在する大規模シナリオでも、実用的かつ効率的に知識保持を行えるようになっています。
5.3 モジュラーアーキテクチャ手法
モジュラーアーキテクチャは、タスクごとに独立したネットワークモジュールを構築することで、タスク間の干渉を効果的に防止する設計手法です。例えば、Progressive Neural Networksでは、新しいタスクが追加されるたびに専用のモジュールを構築し、既存モジュールとの接続を最小限に抑えることで、過去タスクの知識を損なわずに新規タスクを学習できます。
一方、Dynamic Architecture Networksでは、必要に応じてネットワーク構造を動的に拡張し、過去タスクの知識を保持しながら新しい知識を効率的に統合します。これにより、長期的な継続学習環境においても安定した性能を維持でき、タスク数が増えてもモデルの柔軟性を確保できます。
さらに、モジュラーアーキテクチャは転移学習やマルチタスク学習との親和性が高く、タスク間で有用な知識を共有しつつ干渉を防ぐことが可能です。研究段階では、各モジュール間の情報流通を制御するハイブリッド型モデルも検討されており、効率的な知識保持と新規タスク学習の両立を目指した設計が進められています。
5.4 正則化とリプレイのハイブリッド
正則化手法とリプレイ手法を組み合わせたハイブリッド手法により、より強力な破滅的忘却の抑制が可能となっています。正則化によって重要パラメータの更新を制限しつつ、リプレイで過去タスクのデータを学習に反映させることで、忘却だけでなく過学習への対策も同時に行えます。
このハイブリッド手法は、特にタスク数が多い環境で効果を発揮します。過去タスクの重要度に応じてリプレイの頻度やサンプル選択を動的に調整することで、メモリ効率を維持しつつ、モデル性能の安定化を図ることが可能です。
さらに、このアプローチはモジュラー構造との併用も容易であり、複雑な継続学習環境においても柔軟で汎用性の高い設計戦略として利用できます。過去知識の保持と新規タスクの学習を両立させることで、長期的なマルチタスク学習や連続学習におけるモデルの性能向上に寄与します。
5.5 注意機構を利用した手法
Attentionベースの手法は、複数のタスクを同時に学習する際に重要な情報を選択的に保持することで、破滅的忘却(catastrophic forgetting)を抑制するアプローチです。具体的には、学習中に各タスクの重要なパラメータや特徴に対して優先的に学習リソースを割り当てることが可能で、過去タスクの知識を効率的に保護できます。
この手法は、特に複雑なマルチタスク環境で有効です。タスク間での干渉を適切に制御できるため、新しいタスクを学習しても過去タスクの性能低下を最小限に抑えられます。Transformerベースのモデルでは、Attention機構そのものが情報の重要度を動的に判断するため、知識保持における研究が盛んに行われています。
さらに、注意機構はリプレイ(replay)や正則化手法と組み合わせることで、より精密な忘却制御が可能になります。過去タスクの代表サンプルや重要パラメータを意識的に保持しつつ、新しいタスクを学習することで、長期的なマルチタスク学習の安定性を高めることができます。
5.6 動的ハイパーパラメータ調整
破滅的忘却を最小化するためには、学習率や正則化係数などのハイパーパラメータをタスクごとに動的に調整する手法が有効です。具体的には、新しいタスクを学習する際に、過去タスクで重要と判断されたパラメータの更新を制限するなど、微調整を行うことで知識の保持を優先します。
この戦略により、モデルは過去の知識を維持しながら新しい知識を効率的に獲得することが可能です。特に、オンライン学習や長期的な継続学習環境においては、タスク間の干渉を最小限に抑えるために非常に効果的です。
さらに、動的ハイパーパラメータ調整は、正則化手法やリプレイ戦略と組み合わせることで、忘却抑制の精度をさらに向上させることができます。重要パラメータの保護と新規学習のバランスを取ることで、マルチタスク学習や連続学習におけるモデルの性能安定性を高めることが可能です。
破滅的忘却を防ぐ手法には、正則化、リプレイ、モジュラーアーキテクチャに加え、ハイブリッド戦略、Attentionベース手法、動的ハイパーパラメータ調整など、多角的なアプローチがあります。これらを適切に組み合わせることで、継続学習環境においてモデルの知識保持と適応能力を最大化することが可能です。
6. 破滅的忘却の研究動向と展望
破滅的忘却の克服は、AIが継続的に学習できる能力を持つための重要課題です。近年の研究では、メタ学習の手法を活用し、モデルが新しいタスクを学習する際に過去の知識を保持できる仕組みの開発が進んでいます。また、人間の記憶保持や神経回路の特徴を参考にした設計も検討されており、モデルが長期的に知識を保持しつつ、新しい情報を統合できるようにする試みが行われています。
さらに、分散学習や連合学習といったアプローチにより、複数のタスクやデータセットを別々に扱いながら、必要に応じて知識を統合する方法も研究されています。これにより、モデルは異なる環境や条件下でも安定して学習し続けることが可能になり、AIが単なるデータ認識に留まらず、継続的に適応・進化する知的システムとして運用できる可能性が高まります。
おわりに
破滅的忘却(Catastrophic Forgetting)は、AIが継続的に学習を進めるうえで避けられない根本的な課題です。これは、新しい知識の獲得に伴い、過去に学習した知識が意図せず失われてしまう現象を指します。この現象を正しく理解し対策を講じることは、継続学習(Continual Learning)や終生学習(Lifelong Learning)の実現に直結します。
破滅的忘却は単なる性能低下ではなく、モデルの知識蓄積や安定性に深刻な影響を与えます。新しい情報が既存パラメータを書き換えることで、以前の学習成果が損なわれるため、長期的な学習戦略やモデル設計では慎重な対策が必要です。
この課題への対応は、AIが過去の知識を土台に新たな知識を積み上げる「創発的知能」を構築するための基礎でもあります。リプレイ法や正則化法、動的構造法などを活用することで、AIは柔軟かつ安定して学習を継続でき、より高度な知的能力の実現に貢献します。


 EN
EN JP
JP KR
KR